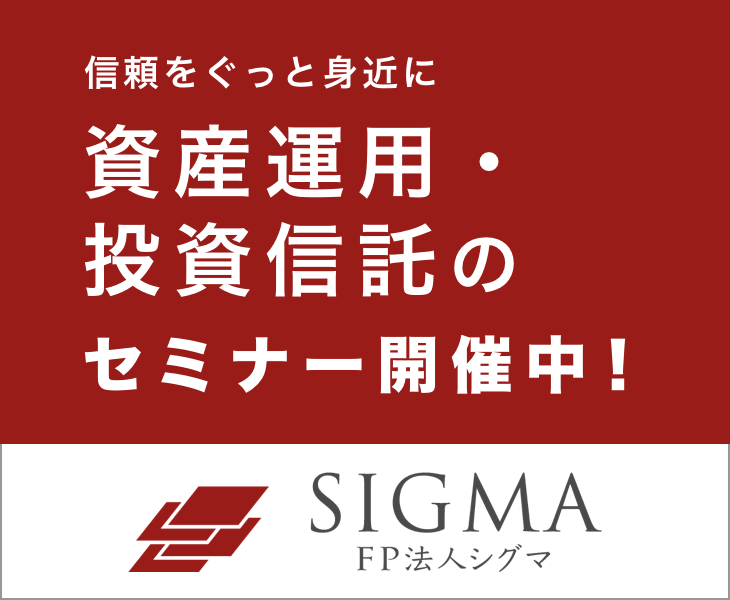投資は難しいもの?
投資は、「難しい」とか「失敗しそう」というイメージがありますね。実際に、なかなかうまくいかずに途中でやめてしまう人が多いのも事実です。では、本当に投資は難しいものなのでしょうか?
証券投資をする際の選択肢として、投資先はいくつかあります。株式や債券、REIT(不動産の投資法人)、また地域では先進国、新興国などに分けられます。そしてそのほとんどが、長期的にみれば上昇を続けており、下落の時期の方が少ないと言えます。実際に私たちがお金を投じる投資信託についても、長期投資をすればマイナスになる可能性が低いとされています。これは本当なのでしょうか?
そこで、今回は長期に運用実績のある投信について調査をしてみました。
ウエルスアドバイザー社のデータによると、20年以上の運用実績がある投信は330本(純資産20億円以上、アクティブファンド、2024年6月末現在。)です。そのうち運用開始以来で現状がマイナスになっているものはわずか3本です。
長期投資をした結果、全体の1%程度はマイナスになってしまったものの、残りの99%はプラスのリターンが得られたことになります。ちなみに、損失になった3本の内訳は、レバレッジ型、テーマ型、ヘッジ付き債券型でした。
この結果から言えるのは、どの投資信託を選んでいたとしても、途中でやめなければ「損をすることはなかった」ということです。
(ただし、このデータには、信託期間が終了したものや純資産が少なくなり償還されてしまった投信などは含まれていないので、「投資信託ならなんでもいい」と言うわけではありません。)
長期運用のパフォーマンス
これらの投資信託の中で最もパフォーマンスが高かったのは、ある欧州株式ファンドでした。28年間の運用でなんと15倍以上の値上がり(年率50.04%のリターン!)となっていました。とはいっても、数ある投資信託の中からこれをピンポイントで選ぶことは難しかったかもしれませんね。
ちなみに、それ以外の投資信託でも全体の8割近く(258本)が2倍以上のリターンを上げており、長期運用の効果が示される結果となりました。
もちろん、最近の株高・円安がパフォーマンスを押し上げているのは事実だと思います。それでも、「概ねどれを選んでいても損することはなく、8割近い確率で資産が2倍になった」のです。このような結果から、投資は決して難しいものではないと言えるのではないでしょうか。
では、どうして投資が「難しい」イメージになってしまうのでしょうか。これは、近年注目されている行動経済学によって解決できるかもしれません。人は、頭ではわかっているものの、ついつい感情的な判断をしてしまいがちです。
行動経済学で読み解く投資家心理
突然ですがここで質問です。あなたなら、次のどちらを選びますか?
質問1
A 確実に9万円もらえる。
B コインを投げて表がでたら20万円もらえるが、裏が出たら
何ももらえない。
続いて、質問2
C 確実に9万円を没収される。
D コインを投げて裏が出たら20万円を没収されるが、表が出たら
何も没収されない。
これは、有名なプロスペクト理論の例ですが、質問1では、多くの人がAを選択するそうです。Aの方が確実性が高いのでメリットがあるように感じますね。ただ、期待値を計算するとBの方が高くなります。
(この事例の場合、Aは100%の確率で9万円がもらえるので、期待値は9万円。Bは50%の確率で20万円がもらえるので、期待値は10万円ですね。)
また、質問2の期待値を計算すると、Dのほうが損をする確率が高いことがわかります。
(C:期待値: -9万円 D:期待値: -10万円)
しかし、現実はDが選ばれることが多くなるようです。
人間は「利益の獲得」よりも、「損失の回避」を強く思考する傾向にあるようです。そして、利益よりも損失の方を2.25倍程度重く受け止めるとも言われています。
これを資産運用に当てはめると、「確率的には長期的にうまくいくことが多くても(前述)、一時的な損失に耐えられなくなる」理由が見えてきます。頭ではわかっていてもとにかく損をしたくない気持ちが、合理的でない判断をしてしまうのでしょう。
前述の330本の投資信託も時期によってはマイナスになることがあります。直近では2018年から2019年の1年間はその9割程度がマイナスですし、リーマンショック時にはほとんど例外なく価格は半分くらいまで値下がりしていました。
「損失回避」の罠から逃れる方法
ポイントは3つあります。
1つ目は、中長期の運用目標を明確にすることです。例えば、「10年後に○○%増やす」「60歳で5000万円にする」などです。中長期的な目標がしっかりしている人は、大きな下落局面でもそれを「途中経過」と考えて乗り切ることができているように思います。反対に、目標が明確でない人は「毎日が結果」のように感じてしまいがちです。本来必要のない売り買いをしてしまうことももあり、結果的にパフォーマンスが悪くなってしまいます。
2つ目は、自分のリスク許容度を知ることです。実は人によって、値下がり時の感じ方は違います。同じように100万円の値下がりだったとしても、仮に1億円を持っている人は1%のマイナスですが、200万円の資産の人であればマイナス50%にもなります。自身の運用資産がどのくらいのマイナスまでなら耐えられるかを予め想定しておくことはとても重要なことです。
3つ目は、下落局面で何が起きているかを知ることです。何が起きているかがわからない時に、人間は最も恐怖を感じます。ある程度の投資知識や経験がある人は、下落理由をしっかりと分析できるため、慌てずに対処できるかもしれません。こんな時に客観的な視点でアドバイスをしてくれる人がいると頼もしいですね。
そういう意味で本当のアドバイザーとは、単にいい商品を選んでくれる人ではありません。上記のポイントを押さえながら、その人に適したプランを提示してくれる人と言えるのではないでしょうか。
また、こんなケースはどう考えたらいいでしょうか。特に年配の方から言われることですが、「もう長期では考えられない」という場合です。結論は簡潔ですね。「リスクの高い投資をしないこと。」です。そのように感じる方は、そもそも運用をしないか、リスクの低い(価格変動が小さい)運用を心がけることが大切です。積極的に殖やそうとするのではなく、例えば年3%~4%程度のリターンを目標にするなど、穏やかな資産運用を実践するのがよいでしょう。

シグマ株式会社
ファイナンシャルプランナー(CFP)
大学卒業後、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。その後、会計事務所系のコンサルティング会社を経て、2013年独立。ライフプランに沿って独立性・専門性の高い資産運用アドバイスを行うためシグマ株式会社を設立。
【講師実績】
NHK文化センター、名古屋証券取引所、高年大学鯱城学園、名古屋市中小企業振興会、地元上場企業、東海東京証券など
【監修書籍】
「老後、教育費…将来が不安!でも、面倒くさいことナシで、お金が貯まる方法、教えてください!」(エクスナレッジ)
「株式投資2年生の教科書」(Gakken)
「教えてまっつん先生!!素人でもわかるお金の授業」(ダイヤモンド社)
「フリーランス大全」(エクスナレッジ)
「投資への不安や抵抗が面白いほど消える本」(Gakken)
【座右の銘】
道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は戯言である
【趣味】
温泉旅行、キャンプ、登山、釣り、ワイン会、読書(特に歴史に関するもの)
シグマ株式会社 金融商品仲介業者 東海財務局長(金仲)第152号
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。